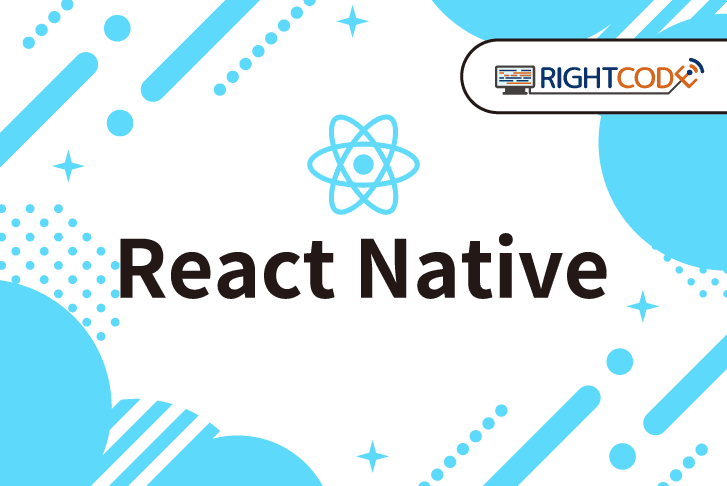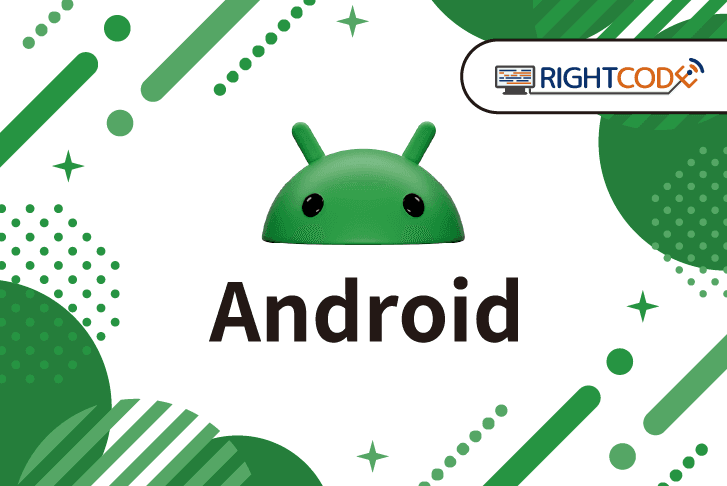Gemini CLIに衝撃 ― 2025年のAI開発環境を語る
IT技術

はじめに
 こやまん
こやまんこんにちは、最近GeminiCLIを活用している "こやまん" です。
今回は、私が実際に使っている AIを取り入れた最新の開発環境 について紹介していきます。
2025年の開発環境
ここ数年でAIは急速に普及し、私たちの業務環境にも深く入り込むようになってきました。
AIツールを導入することで、作業のスピードアップや効率化が期待できる一方で、過度に依存すると誤りやリスクを見逃したり、開発者自身の判断力が弱まる懸念もあります。
そのため、AIを開発者の代替ではなく「開発力を拡張するパートナー」として活用しています。
現在、私が利用している主なAIツールは以下の通りです。
| Gemini CLI | 実装で利用 |
| Jules | 実装で利用 |
| Github Copilot | PRの概要表示・レビューで利用 |
| Devin | PRレビューで利用 |
| Gemini | 汎用的に利用 |
| ChatGPT | 汎用的に利用 |
Gemini CLI
Gemini CLIは、Googleが2025年6月25日に発表されたAIエージェントで、私が最も感動したAIエージェントでもあります。
Gemini CLIでは、GEMINI.mdというファイルをプロジェクトのルートディレクトリに配置することで、生成されるコードや提案の品質が向上します。
Gemini CLIを初めて導入した時に作った "まるばつゲーム" のGEMINI.mdを見てみましょう。
実は、このGEMINI.mdも、Gemini CLIに「まるばつゲームを作るので、GEMINI.mdを考えてみて」と伝えて生成してもらいました。
必要に応じて、GEMINI.mdに守ってほしいルールや、特に注意してほしい点を明記しておくことで、Gemini CLIが、プロジェクトの規約に沿った形でタスクを遂行してくれるようになります。
GEMINI.md
1# Gemini Project Configuration for まるばつゲーム
2
3## 1. プロジェクト概要
4
5これは、ブラウザで動作する「まるばつゲーム(三目並べ)」です。
6
7- **技術スタック:** HTML, CSS, JavaScript (フレームワークは使用しません)
8- **目的:** シンプルで分かりやすいコードで、基本的なゲームロジックを実装します。
9
10## 2. 実行方法
11
12- **開発:** `index.html` ファイルを直接ウェブブラウザで開いてください。
13- **テスト:** このプロジェクトでは、現時点で自動テストの仕組みはありません。手動でゲームをプレイして動作を確認してください。
14
15## 3. コーディング規約
16
17- **ファイル構成:**
18 - `index.html`: ゲームの骨格となるHTML
19 - `style.css`: ゲームの見た目を整えるCSS
20 - `script.js`: ゲームのロジックを記述するJavaScript
21
22- **JavaScript:**
23 - 変数名はキャメルケース(`camelCase`)を使用してください。
24 - DOM操作は、`document.getElementById` や `document.querySelector` を適切に使い分けてください。
25 - ゲームの状態(盤面、現在のプレイヤーなど)は、明確な変数で管理してください。
26
27- **CSS:**
28 - セレクタはシンプルに保ち、IDセレクタやクラスセレクタを適切に使用してください。
29 - BEM(Block, Element, Modifier)のような命名規則を参考にすると、CSSが整理しやすくなります(例: `.board`, `.board__cell`, `.board__cell--x`)。
30
31- **HTML:**
32 - セマンティックなHTMLを心がけてください。
33
34## 4. その他
35
36- **実装する機能:**
37 - 3x3のゲーム盤の表示
38 - プレイヤーがセルをクリックすると、〇 と × が交互に表示される
39 - 縦・横・斜めのいずれかが揃った場合に勝者を判定する
40 - 引き分けを判定する
41 - 勝敗が決まったら、結果を表示する
42 - ゲームをリセットするボタン
43
44- **注意点:**
45 - まずは基本的なゲームが動作することを最優先します。
46 - コードには、処理の内容が分かりやすくなるように適度にコメントを追加してください。上記のGEMINI.mdを用いて、生成したまるばつゲームは以下のようなものになりました。

一発で問題なくまるばつゲームが生成できたのは驚きでした。
ゲーム自体も問題なく動作しました。
生成されたコードを確認してみます。
以下は、Gemini CLIで生成されたjsのコードの一部です。
1const cells = document.querySelectorAll('.cell');
2const gameStatus = document.getElementById('game-status');
3const resetButton = document.getElementById('reset-button');GEMINI.mdに記載してある "変数名はキャメルケース(`camelCase`)を使用してください。"というルールに沿って、jsの変数名がキャメルケースで生成されていることが確認できます。
実際に動かしたり、全てのコードを確認したい方は以下の手順を実行してみてください。
1. まるばつゲームが格納されているリポジトリをクローン
1git clone git@github.com:KonoLevel1/mac-local-app.git2. まるばつゲームを起動
1open mac-local-app/app/marubatu-game/index.html注:Mac OSかつ、Gitコマンドを導入済みの環境での操作を想定しています。
格納先のGitHubリポジトリは以下をご確認ください。
https://github.com/KonoLevel1/mac-local-app
Jules
Julesは、Googleが2025年8月6日に正式リリースした AIコーディングエージェント です。
GitHubリポジトリと連携してタスクを実行し、プラン → 承認 → 実行 → 結果確認 という流れで進む点は、Terraformのワークフローに近い印象を受けます。
操作はGUIベースが中心ですが、今後はさらなる軽量化やエディタ統合が期待されます。
GitHub Copilot
GitHubが2022年6月に正式リリースした、定番のAIコード補完ツールです。
現在はPR(プルリクエスト)周りで大きな効果を発揮しており、レビュワーに設定すると以下のようなことが可能です。
- 自動でPRの概要をまとめる
- 初期レビューを行い、問題点を指摘
他の開発者によるレビューが始まる前に指摘が入ることで、レビュワーの指摘箇所が減少し、開発効率が向上します。
さらに、.github/copilot-instructions.md を用意することでレビュー言語を変更できます。例えば、以下のように記載すると日本語でのレビューが可能になります。
.github/copilot-instructions.md
1## 使用言語
2日本語でレビューしてください。また、VSCodeに拡張子でインストールすることで、高精度のコードやコメントの予測を行ってくれるため、とてもありがたい存在です。
Devin
Cognition社が2024年に発表したAIエージェントです。GitHubと連携し、特に慎重に実装を行う箇所などのPRのレビューで利用しています。
Gemini
GeminiはGoogleが2023年12月6日に正式リリースした大規模AIモデルです。
弊社では全社員が有料プランの Gemini Pro を利用しており、汎用的なタスク(調査、資料作成、議事録要約など)で幅広く活用しています。
特に、GeminiやChatGPTは、画像生成機能や、画像を添付すると画像を解析する機能が備わっており、重宝しています。
ChatGPT
最後に紹介するのは、知名度No.1の ChatGPT。
OpenAIが2022年11月30日に公開して以来、世界中で使われるAIとなりました。
私は主に以下の用途で利用しています。
- ドキュメントの校正
- テキスト要約
- エラー発生時の原因調査
ただし、ChatGPT(無料版や個人向け有料版)では 入力データが学習に利用される可能性がある ため、セキュアな情報を扱う場合は Enterpriseプラン を利用するのが推奨されます。
IT業界のAIの動向
2025年は、AIの現場への浸透がより加速した年だと強く感じています。
AWSサミットやFindy社主催の『AI×開発組織サミット』などにも参加し、各社でAI活用が加速する一方で、その導入に伴う新たなリスクや課題も浮上していることを実感しました。

いずれのイベントでも、AI導入による業務連携の効率化や開発速度の向上といった利点が強調されていました。一方で、セキュリティリスクへの懸念や、AIに依存することで開発者自身のコーディング力が伸びにくくなる課題も指摘されています。今後は、こうした利点と課題の両面を踏まえ、AIと適切に向き合いながら柔軟に対応していくことが求められます。
技術を扱う職種において、もはやAIは避けて通れない存在と言っても過言ではありません。
しかし、AIの活用そのものが目的化してしまっては本末転倒です。常に「課題を解決することこそが最終目的」であるという原点を忘れず、AIと人の力をバランスよく掛け合わせながら、より良い開発や価値創出を目指していきたいですね。
今後も弊社ではAI活用の最新動向や実践的な事例を継続的に発信してまいります。
ぜひ、あわせて下記の記事もご覧ください。
AI関連記事はこちら
ライトコードでは、エンジニアを積極採用中!
ライトコードでは、エンジニアを積極採用しています!社長と一杯しながらお話しする機会もご用意しております。そのほかカジュアル面談等もございますので、くわしくは採用情報をご確認ください。
採用情報へ
おすすめ記事

CloudRunのネットワークエラーに遭遇
2025.11.25